news新着情報
親が片付けられない問題を解決する「3つのステップ」:実家の片付けを成功させるアプローチ方法について解説します2025.10.01
「実家がゴミ屋敷のようになってきた」「親が何を言っても物を捨ててくれない」—。
親御様の高齢化に伴い、実家の片付けは多くのご家族にとって避けて通れない深刻な問題となっています。この問題は、親子の間に亀裂を生み、最悪の場合、親のゴミ屋敷対策が必要なほどに深刻化することもあります。
しかし、ご安心ください。適切な知識と段階的なアプローチ、そして必要に応じたプロの力を借りることで、この課題は必ず解決できます。このガイドでは、親の片付けられない問題を「3つのステップ」で解決するための具体的な方法を、親の心理に寄り添いながら解説します。
親が片付けられない問題を解決する「3つのステップ」
親の片付けられない問題に対処するためには、感情論ではなく、冷静に状況を分析し、戦略的に動くことが不可欠です。まずは、現状を把握し、解決までの道筋を明確にしましょう。
状況別!実家の片付け問題の深刻度チェックリスト
親御様の状況を客観的に把握することが、最初の一歩です。
以下のチェックリストで、実家がどの段階にあるかを確認しましょう。
初期段階(軽度):
床の一部に物が置かれ、足の踏み場がない部分がある。
賞味期限切れの食品が少量ある。
来客を拒むようになってきた。
進行段階(中度):
生活動線(トイレ、風呂、台所)にも物が積み上がり始めている。
一部の家具(椅子、テーブル)が物で埋もれて使用不能。
カビやホコリが目立ち、異臭がわずかにする。
深刻段階(重度):
床全体が物で覆われ、室内を移動する際に物を跨ぐ必要がある。
害虫(ゴキブリ、ネズミなど)の発生を確認している。
火災報知器や暖房器具の周辺にも物があり、危険な状態にある。
(親のゴミ屋敷対策が必要なレベル)
親が片付けられない状態を放置するリスク(健康・安全・関係悪化)
実家の片付けを先延ばしにすることは、以下のような深刻なリスクを増大させます。
健康リスク:
ホコリやカビによる喘息やアレルギーの悪化。
物の山につまずくことによる転倒事故・骨折のリスク増大。
高齢者の骨折は寝たきりの直接的な原因になり得ます。
安全リスク(火災・災害):
ストーブなどの熱源の近くに可燃物が積まれ、火災の危険性が高まります。
地震などの災害時に、物が倒れてきて避難経路が塞がれる危険があります。
家族関係の悪化:
片付けを巡る親子の言い争いが増え、親御様の孤立や片付けられない親心理の悪化を招きます。
解決へのロードマップ:個人での対策→専門家への相談→業者依頼
この問題を解決するためには、以下の段階的なロードマップが必要です。
ステップ1:親の「心の整理」
親の心理、片付けられない親心理を理解し、共感的なコミュニケーションで信頼関係を構築する。
⇩
ステップ2:親子で進める「具体的な片付け」
親に負担をかけない「小さなエリア」から着手し、生前整理を口実にした段階的な物の減らし方を実践する。
⇩
ステップ3:【最終手段】「専門業者への依頼」
自分たちだけでは限界と判断した場合、信頼できる生前整理業者選び方に基づき、遺品整理士などの専門家がいる業者に依頼する。
それぞれのステップについて、以下でより詳しく説明していきます。
ステップ1:親が片付けられない「根本的な原因」の理解と心理的アプローチ
実家の片付けの成功は、このステップにかかっています。親の心理を理解せずに強引に物を捨てさせようとすると、親子関係の修復が困難になるだけでなく、片付けがリバウンドする原因にもなります。
なぜ親は片付けられないのか?高齢者に多い3つの主な原因
親御様が物を溜め込むのには、理由があります。片付けられない親心理を深く理解しましょう。
身体機能の低下と「認知症」の初期症状
- 身体機能の低下:物の持ち運び、高い場所への手の届きにくさ、細かい判断力の低下など、片付けを物理的に行いづらくなります。
- 認知症の初期症状:認知機能の低下により、「いるもの/いらないもの」の判断が難しくなったり、片付けのプロセス(ゴミ出しの曜日、どこに何をしまうか)が理解できなくなることがあります。
ため込み症(ホーディング障害)の可能性と特徴
- ため込み症(ホーディング障害):精神疾患の一つで、「物を捨てることに対して耐えがたい苦痛を感じる」病態です。単なる「だらしなさ」ではなく、専門的な治療が必要なケースもあります。
- 特徴:物の価値に関係なく全てを溜め込む、物が無くなると強い不安を感じる、などがあります。
精神的な孤独感や「もったいない」意識の増大
- 孤独感:定年退職や配偶者との死別などにより、精神的な孤独感を抱き、物が心の隙間を埋める代わりになっているケースがあります。
- 「もったいない」意識:戦後の貧しい時代を経験した世代に強く、「いつか使う」「まだ使える」という意識が、物の手放しを妨げます。これはため込み症とは異なり、価値観に根ざした行動です。
親の気持ちに寄り添うための「聞く」声かけ術とNGワード
親御様の自己肯定感を損なわず、協力を得るための「声かけ」が最も重要です。
| 聞く声かけ術(OKワード) | NGワード(絶対に避けるべき) |
| 「大変だね、一緒にやろうか?」 | 「なんでこんなに汚いの!?」 |
| 「安心・安全のために少し考えよう」 | 「全部捨てなきゃだめだよ」 |
| 「〇〇(思い出の品)の話を聞かせて」 | 「あなたのせいで家が大変だよ」 |
| 「ここだけきれいにしてみない?」 | 「もう年なんだから、やめてよ」 |
ポイント:否定や批判はせず、「健康と安全のために」という親御様の利益を軸に提案し、親御様の経験や思い出を尊重して話を聞く姿勢を徹底してください。
家族間の意見対立を避けるためのコミュニケーション戦略
兄弟姉妹など複数の関係者がいる場合、意見が対立しがちです。
- 役割分担の明確化:「親の心理的ケア担当」「業者との連絡・費用担当」「実際の作業担当」など、各々の役割を明確に分担します。
- 情報の共有:親御様との会話内容や、進捗状況を定期的に共有する場(オンライン会議など)を設け、認識のズレを防ぎます。
- 親の意思を最優先:どんな場合でも、**「親の意思を尊重する」**ことを共通認識とし、強引な片付けはしないことを徹底します。
ステップ2:親が片づけを嫌がる時の「具体的な片付け」実践マニュアル
実家の片付けを物理的に進める段階です。
ここでは「捨てる」ことに注力するのではなく、「親御様が気持ちよく生活できる空間を取り戻す」ことを目標とします。
最初の一歩:親に負担をかけない「小さなエリア」からの着手
いきなり家全体や、親御様のため込み症が特にひどい部屋から着手するのは逆効果です。
- 片付けの着手点:親御様にとって最も関心が薄く、しかし安全に直結する小さなエリア(例:玄関の靴、リビングのテーブルの上、冷蔵庫の中の古い食品)から始めます。
- メリット:小さなエリアでの成功体験が、親御様に「自分にもできる」という自信を与え、次のステップへの協力に繋がります。
片付けのルール:捨てる・売る・譲るの判断基準と親の納得を得る方法
物を「捨てる」という言葉を避け、「仕分け」という言葉を使います。仕分けの基準を親御様と一緒に設定します。
- 残すもの:今後1年以内に使うもの、思い出の品(写真、手紙など)。
- 売る/譲るもの:まだ使えるが、今後使わないもの(ブランド品、食器、家具)。
- 捨てるもの:壊れている、汚れている、賞味期限が切れているもの。
親の納得を得る方法:捨てると決めた物でも、すぐにゴミ袋に入れたりせず、「一時保管ボックス」に入れ、親御様が「本当にこれで良い」と納得するまで時間をおく、というプロセスを挟むことが重要です。
捨てるものを無理強いしない!思い出の品の整理における注意点
実家の片付けで最もデリケートなのが思い出の品です。
- 感情に寄り添う:「これは捨てて」ではなく、「これは本当に大切なものだね。写真だけ残して、物は手放せないかな?」と提案します。
- デジタル化の提案:大量の写真や手紙は、スキャンしてデジタルデータ化する**「デジタル生前整理」**を提案し、物理的な量を減らす工夫をします。
- 「思い出ボックス」の設置:「思い出は大切だから」と、残すことにした思い出の品だけを収納する専用のボックスを設置し、それ以外の物を処分対象とすることで、親御様の心の整理を促します。
生前整理を口実にした段階的な物の減らし方
生前整理は、「元気なうちに自分の人生を振り返り、身の回りのものを整理して、残された家族に負担をかけない準備」というポジティブな意味合いで伝えます。
- ポジティブな動機付け:「生前整理をしておくと、万が一の時にあなたが大切にしていたものがちゃんと次の世代に引き継げるよ」「今のうちに整理しておけば、老後の生活がもっと安全で快適になるよ」といったメリットを強調します。
- 「〇〇を活かす」という視点:「この食器、親戚の△△ちゃんが欲しがってたよ」など、売る・譲るといった形で**「物を活かす」提案をすることで、「もったいない」**意識を解消しやすくなります。
ステップ3:【最終手段】実家や親の片付けを専門業者に依頼する
親子での片付けに限界を感じた場合や、親のゴミ屋敷対策が必要な深刻な状態に陥った場合は、迷わず専門業者に依頼することを検討しましょう。
どんな時に専門業者(生前整理・遺品整理)に依頼すべきか?
専門業者の利用は、時間と労力を大幅に節約し、親子の関係悪化を防ぐための賢明な選択です。
- 依頼すべきケース:
- 物理的な量が多すぎて、家族の手だけでは数週間〜数ヶ月かかる場合。
- 片付けの際に親子間の衝突が絶えず、関係が悪化している場合。
- 遠方に住んでおり、頻繁に実家へ行くことが難しい場合。
- 害虫や異臭が発生しており、専門的な特殊清掃が必要な場合。
- 生前整理業者選び方に悩むほど、親御様のこだわりが強い場合。
専門業者は主に生前整理(存命中の整理)と遺品整理(死後の整理)を専門としていますが、どちらも実家の片付け全般を請け負っています。
実家の片付けで後悔しない!悪徳業者を見分ける5つのポイント
悪質な業者に依頼すると、高額請求や貴重品の盗難といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。
- 極端な安値の見積もり
他社より突出して安い場合は、後から追加料金を請求されるリスクがあります。 - 詳細な見積もりを出さない
「一式」で済ませず、作業内容や費用項目を詳細に説明するか確認しましょう。 - 電話での即決を迫る
訪問見積もりを拒否したり、その場での即決を強く迫る業者は危険です。 - リサイクル品の買い取りを強要する
買い取りを前提に作業を進め、不当に安く買い叩こうとする業者には注意が必要です。 - 資格や実績を明記していない
後述する遺品整理士などの専門資格や、明確な施工事例があるか確認しましょう。
信頼できる業者を選ぶためのチェック項目
生前整理の業者を選ぶ際の考え方をお教えいたします。参考にしてください。
1. 専門性と実績:遺品整理士など資格の有無と施工事例
ウェブサイトに、写真付きで具体的な施工事例(ビフォーアフター、作業内容、お客様の課題)が豊富に掲載されているか。
2.経験と信頼性:お客様の声・顔の見えるスタッフの紹介
お客様の声が、手書きや動画など、信頼性の高い形で掲載されているか。
3.作業を行うスタッフの顔写真やプロフィールが公開されているか(経験の証明)。
顔が見えることで、依頼への安心感が高まります。
4.明確な料金体系:費用相場と追加料金が発生するケース
ウェブサイトに料金の明確な相場が記載されており、追加料金(トラックの駐車料金、階段料金、特殊清掃費など)が発生する条件を事前に説明してくれるか。
見積もりを依頼する際のチェックリスト(相見積もり、対応範囲)
実家の片付けを成功させるには、複数の業者から相見積もりを取ることが必須です。
- 相見積もり:最低3社から見積もりを取り、料金と対応内容を比較する。
- 対応範囲の確認:どこまでを基本料金に含んでいるか(仕分け、運び出し、清掃、不用品の処分、リサイクル、合同供養など)を明確にする。
- 貴重品の取り扱い:現金、通帳、契約書、思い出の品などの貴重品の探索・保管方法について、具体的な手順を確認する。
親の片付け問題を解決した後の持続的な「予防策」
一時的に実家の片付けが完了しても、親御様の片付けられない親心理が解決されていなければ、すぐにリバウンドしてしまいます。持続的な予防策が必要です。
リバウンドを防ぐための「整理収納」の継続的な仕組み
- 物の「住所」を決める:「定位置管理」を徹底するため、すべての物にしまう場所(住所)を決め、親御様にも分かるようにテプラなどで明記します。
- 定期的な「点検」:月に一度、ご子息・ご息女が実家を訪問し、**「点検」**と称して小さなゴミの回収や、収納場所からの溢れをチェックします。
- ワンイン・ワンアウト:新しい物を一つ買ったら、古い物を一つ手放す**「ワンイン・ワンアウト」**のルールを親御様と合意し、習慣化を試みます。
地域包括支援センターなど外部機関との連携方法
親御様の片付けられない親心理や、認知症の進行が疑われる場合は、行政や医療機関との連携を検討しましょう。
- 地域包括支援センター:高齢者の総合相談窓口です。介護予防や医療機関への連携、親のゴミ屋敷対策などの相談にも応じてくれます。
- 専門医:ため込み症や認知症が疑われる場合は、専門医(精神科、心療内科)への受診を勧め、根本的な治療とアドバイスを受けることが、問題の解決に繋がります。
親が片付けられない悩みを持つ家族のための相談窓口
この問題に一人で悩む必要はありません。
- 各自治体の福祉窓口:高齢者・ゴミ屋敷対策の相談窓口が設置されている場合があります。
- (一社)遺品整理士認定協会:遺品整理士の資格を持つ信頼できる業者を紹介してもらえます。
- NPO法人など:生前整理や実家の片付けの悩みに特化したNPO法人やボランティア団体も存在します。
まとめ:親の片付け問題は「物の整理」ではなく「心の整理」
親が片付けられない問題、実家の片付けを乗り越えるための道筋が見えてきたでしょうか。
この記事を通して最もお伝えしたかったのは、「実家の片付けは、親の経験と人生を尊重する『心の整理』であるため、無理強いするわけではなく、しっかりコミュニケーションをとって進めてもらいたい」ということです。
もし、ご自身での解決が難しく、深刻な状態にある場合は、遺品整理士などの専門性と経験を持つ業者に頼るという選択肢は、決してネガティブなものではありません。それは、**「親の安全」と「ご家族の安心」**を守るための、賢明で、愛のある決断です。
いますぐ始めるべき3つのアクション
親御様との対話の時間を作る
まずは「なんで片付けないの?」ではなく、「健康と安全について一緒に考えたい」という姿勢で、親御様の気持ちを聞くことから始めましょう。
実家の深刻度とゴールを明確にする
本記事のチェックリストを参考に、実家の片付けの現状を冷静に把握し、**「最終的にどういう状態にしたいか」**というゴールを明確にします。
信頼できる業者の情報を集める
生前整理の業者の選び方を参考に、地域で評判の業者や遺品整理士のいる業者を2〜3社ピックアップし、無料見積もりや相談窓口に問い合わせる具体的な行動喚起をしましょう。
親御様にとって、住み慣れた実家が、いつまでも安全で快適な場所であるように。そして、ご家族の皆様が笑顔で暮らせるように、今日から一歩踏み出しましょう。
【北九州エリア限定】実家の片付けは「おうちサポート」にご相談ください
本記事を読み、いよいよ一歩踏み出そうと決意された北九州エリアにお住まいの皆様へ。
私たちおうちサポートは、実家の片付け、ごみ屋敷、不用品回収、遺品整理といった、ご家族だけでは難しいデリケートな問題を専門的に解決するプロフェッショナルです。特に「親を傷つけたくない」「遠方で作業が進められない」といったご子息・ご息女の悩みに寄り添い、親御様の心の整理を尊重したサポートを徹底しています。
<おうちサポートの強み>
代表自ら対応
ご依頼から作業完了まで、責任と経験を持った代表が直接対応するため、意思疎通のズレがなく、きめ細やかなサービスを提供します。
女性スタッフ対応
親御様、特に女性のお客様が安心できるよう、ご要望に応じて女性スタッフが対応します。親の気持ちに寄り添った丁寧な仕分け・整理を心がけています。
スピード対応
ごみ屋敷や急を要する不用品回収など、緊急度の高いご依頼にも、迅速な見積もりと作業で対応し、安全を最優先に問題解決いたします。
処分量が多いほどお得
実家の片付けで大量の不用品が出る場合でも、積み放題プランなど、処分量が多いほどお得になる明確な料金体系をご提示します。
「実家の片付け」は、専門性と信頼性が最も重要です。まずは無料相談・無料見積もりで、お悩みをお聞かせください。親御様にもご納得いただけるよう、透明性の高いサービスをお約束します。
親御様にとって、住み慣れた実家が、いつまでも安全で快適な場所であるように。
そして、ご家族の皆様が笑顔で暮らせるように、私たちおうちサポートが全力でサポートさせていただきます。


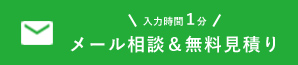
 電話
電話 メール
メール 公式ライン
公式ライン